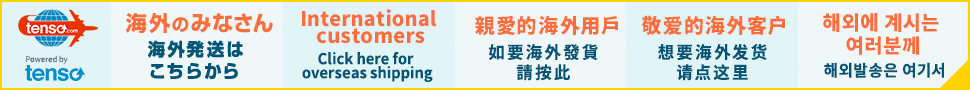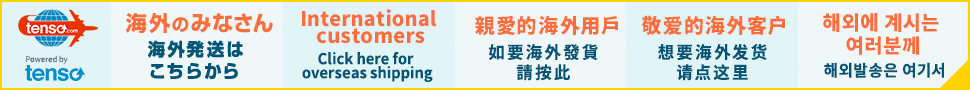もともと唐(中国)から伝来の細工紙を唐紙と呼び、のちに襖紙そのものを“からかみ”と言うようになりました。 日本の建築物に、襖・障子が使われるようになったのは、平安時代以後のことで、始めは、色紙を貼ったり、絵画を描いて装飾していましたが、やがて、からかみを使うようになりました。 もともと唐(中国)から伝来の細工紙を唐紙と呼び、のちに襖紙そのものを“からかみ”と言うようになりました。 日本の建築物に、襖・障子が使われるようになったのは、平安時代以後のことで、始めは、色紙を貼ったり、絵画を描いて装飾していましたが、やがて、からかみを使うようになりました。
からかみの製造は、彫刻した板木を用いた木版が中心で、普通の木版のように、バレンを使わず、直接手のひらで摺るため、木版の彫りは深く、出来上がりにも柔らかみがあります。一般の住居に襖が用いられたのは、江戸時代中期で、木版摺りの紙を貼る事が普及しましたが、そのころの紙の製造技術では、奉書紙程度のものしか作れず、襖全体を貼るのに12枚を必要としていました。
伝統的な木版によるからかみは、江戸時代中期に京都で13の業者があり、東京・大阪にもそれぞれ加工業者がありましたが、機械刷りに圧迫されて減少し、現在京都に弊社を含め2業者が残るのみとなりました。 京都の伝統的な木版摺りの技法によるからかみは、その文様も、中国的なものをはじめ、日本文化に深く根をおろし、日本の風土にあった、日本の感覚を反映したデザインが豊かに残っており、寺院や離宮・茶室・料亭などの需要に支えられ、その技法は、現代に伝承されています。
私たち株式会社丸二では、“京からかみ”を建築と切り離せない内装の一環として、また現代建築の住空間を満たす一つの素材としてご提案させて頂いております。 古都千年の歴史に育まれた、優美な“京からかみ”。 多くの皆様のご利用を心よりお待ち申しております。
|